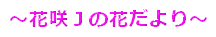

地植えのシデコブシ花芽です。
暖かそうなうぶ毛に包まれています。
花咲Jがその昔、愛知県伊良湖岬に近い椛(なぐさ)という所にある桃花シデコブシの群生地(愛知県指定天然記念物)を見に行った時、落ちていた種を拾ってきて生えた木です。
天然記念物だから種を拾うのも良くないことでした・・・。
現在は3本が最大高さ1.8mに育っています。
・ 2012.1.1 新年を迎えることができました
・ 2012.1.10 冬の園芸作業いろいろ
・ 2012.1.29 農繁期
・ 2012.1.29 農繁期
| 戻る | トップへ | 販売品コーナーへ | 購入のご案内へ | 送料のご案内へ | お問い合わせへ | レポートコーナーへ |
2012.1.1 新年を迎えることができました
明けましておめでとうございます。
今年は、東北大震災や福島原発災害に遭われた方々に、少しでも希望の陽がさす年になりますことを祈念いたします。
新年を迎えて家の周りにある植物たちを見てみました。
これらの植物のように、自然のままに気持ちゆったりと過ごしていきたいものです。

鉢植えのクリスマスローズに力強い花芽が伸びています。
これも花咲Jが交配したものですが、初花はどんな花が咲くやら・・楽しみです。

柿の木の株元に植えたクリスマスローズの方は、まだ小さな花芽です。
家の西側にあり、家の影と柿の葉で日光は遮られる場所ですが、大きな葉を付けています。
花は茶色系のイマイチかイマニくらいですが、咲くとかわいいです。
冬に咲く花として貴重な花です。

道端に生えたローズマリー
当宅西側の道路との境界線上に実生したものですが、横にあるコンクリート擁壁の上にはローズマリーが植えてあるため、こぼれ種から発芽したと思います。
コンクリートの隙間は数ミリしかないのにも関わらず、幹は直径2cm近くの太さで、冬に青い小花を咲かせてくれます。
花咲Jが車にひかれないよう、道路側へ伸びる枝はすべて切り取り、盆栽風に剪定しています。

ホームページにたびたび登場しているヘゴ着けランです。
右側のミニカトレアは10月24日に既に咲いていたものですが、もう50日間も咲き続けています。
干からびてドライフラワーになってしまったかと心配するときがあります。
ランは不定期に年2回咲くものがよくありますが、秋頃から寒い季節に向けて咲く花は同株でも花持ちがいいです。
バルブを増やして成長するタイプのランは、新バルブ毎に一つの花を付けます。
中には年中成長するものもありますが、冬を越して暖かくなるに従って成長したり、真夏の暑さで休眠して涼しくなって成長を始めたり、一つのバルブが出芽から成熟するまで1年間を要さないため、花を何回も楽しめます。
2012.1.10 冬の園芸作業いろいろ
冬は植物も休眠状態のものが多く、世間一般的にはあまり園芸作業も活動的ではありません。
施設園芸農家として再出発した花咲Jは、年中こなしきれない色んな作業に明け暮れています。
いよいよ皇帝ダリアも終演?の時を迎えました。
メキシコ原産の植物とあって、日本では寒さに耐えられないようです。
12月であっても霜に当たると即、葉が縮れて黒変してしまいます。
今冬は1月2日になるとほとんどすべての葉が縮れてしまいました。
2日の朝、コンクリート地面が少し濡れていたことから、夜中にみぞれでも降ったのかも知れません。

霜に当たったのか、葉が縮れてしまった皇帝ダリアです。
今日(8日)は1年間いろいろと楽しませてくれた皇帝ダリアを伐採します。

葉腋に伸びた新芽には大きく膨らんだつぼみも見えますが、新芽の葉も縮れてしまい、花が開くことは不可能です。
1年経たずして最大高さ3m以上にまで伸びた9本の幹を、地上約30cmで伐採しました。
幹は太いのですが、草本ゆえにのこぎりで簡単に切れます。
欲の深いじいさんは幹を節々で細かく切り、挿し木としました。
生命力の旺盛な皇帝ダリアは、寒中に挿し木して春にはもう新芽と根が出てきます。
挿し木は霜に当てないことと、凍らない温度が保てられればよいです。

前回記載の道端に生えたローズマリーですが、陽もうららかな本日(10日)花咲Jが美術的センスも剪定技術もないまま(本人は多少なりともあるように思っている。)散髪いたしました。
枝間が透いてさっぱりしたような感じです。

住宅西面の道路端という厳しい環境と危険のなか、今年も車に轢かれず、元気でいてもらいたいものです。

道端盆栽ローズマリーの花芽もだいぶ切り落としてしまいましたが、小さくて目立たないとは言え、青色の小花(長さ12mm)をたくさん咲かせます。
ローズマリーの枝先はハーブとして肉を焼く時の香味料などになります。
花は小さくとも、花の少ない冬に咲くのが取り柄です。
乾燥した土壌を好む常緑低木で、ハーブであるせいか病害虫もほとんど寄り付きません。
苗木を定植すると成長は旺盛で、樹形を保つには年2回くらいの剪定が必要になります。
その点、鉢植えは根の成長も制限されるせいか、それほどの剪定は必要になりません。
今まではさほど手入れしなかったのですが、道路端にあって通行人の人々にも見られるため、小奇麗にと一応剪定してみました。
水苔植えのランは正月から植え換え作業に入ります。
この時期の植え換えはちょっと早いのですが、量を多くこなすにはやむを得ません。
花咲Jはサラリーマン時代、あまりランに手をかけられず、植え換えもせずに水だけやっていたような状況だったので、鉢植えの蘭の根が縦横に絡み合い手がつけられない有様のものもあります。
植え込む時間と同じくらいに根をほぐす時間がかかります。
でも、この植え換えが園芸の一番の楽しみのような気もします。
2012.1.29 農繁期
当園、園芸楽の農家としての農繁期は正月から始まり、5月くらいまで植え換え作業などが続きます。
花咲Jはサラリーマン時代に満足な管理ができなかったため、温室内のすべての鉢を植え換えたいのですが・・。
特に水苔で植えてあるランは10年以上、植え換えていないものが多くあり、それらは本体が鉢を乗り越えて、中には二つ先の鉢まで行って生きているものもあります。
そうなると鉢内の水苔は黒い粉状になるために根は鉢内へ向かって伸びず、鉢上を縦横に伸び回り、植え換え時にそれをほぐすのは知恵の輪を解くように時間がかかります。
フウランのような単茎種はこのような状況でも何とか枯れずに生きていますが、バルブが増えて伸びていくものや地生蘭は枯れるものも多くなります。
さらに悪いことに、この時期はスキーシーズンと重なり、身体のあちこちに古傷のある花咲Jはそれでも老体の自覚が薄く、ふらりと日帰りスキーへ出かけてはふらふらになって帰ってきます。
園芸楽の農繁期はこういう状態で非常に忙しい有様です。
昨年の植え換えからヘゴ着けをこつこつと作っていますが、ヘゴ着けランのページにありますように、しっかり着生するまでにはやはり2年以上の栽培管理を要します。
作成したものを販売品コーナーへリストアップしたくてもできない状態で、ヘゴ着け以外の植え換えも遅れてしまうために焦りも感じている次第です。

再々登場のミニカトレアで3ヶ月も咲き続けています。
写真左側の1花は花弁に汚れが出てきました。
ミニカトレアでも小輪の花は特に長持ちします。
冬にかけて、温室ではなく寒い場所で咲いてくれると長い間、楽しませてくれます。
このヘゴ着けは家の敷地内にある小さなガラスフレームに入れてあり、加温はしません。
洋ランなども長年かけて徐々に低温に慣らすと、品種にもよりますが、結構、耐寒性が出てきます。
昔、無加温の車庫内で大輪のカトレアを何鉢か作っていた時に、一晩マイナス4〜5℃まで下がった日があり、1日ですべて枯れてしまいました。

秋から冬にかけて園芸店でパンジーなどとともに売られているアリッサムです。
花が小さくて、以前はあまり好きな花ではありませんでしたが、植えてみると1株で直径30cm以上に育ち、なかなか強い香りを出すため、最近は毎冬、鉢やプランターに植えています。
日当たりを好む草花で、5月まで楽しませてくれます。

1月8日に伐採した皇帝ダリアの挿し木の様子です。
長さ10cm程度に切断してあり、節(葉柄)から芽を出しますが、根はどこから出るのでしょう。
茎の切断面か、節部か、発根に成功したら確認してみます。

アリドオシの実です。
小さな木では実が付かず、付いてもまばらに付くことが多いです。
葉柄に鋭いとげがあり、時々ちくちくと刺されますが小さくて(写真は直径6mm)かわいい実です。

クンシランの実です。
草姿が大きいために実も大きくなります。
現在、実が色づき始めていますが、オモトなどに比較すると色・形が今一つの感じです。

この時期に咲くミニカトレアです。
鉢を持ち出したくても棚上で根が絡まりあい取り出せません。
切り花で出荷することもありますが、また写真を撮ってみました。
日本に自生するランの花は日本人の感性に合ってとても良いのですが、洋ランの華やかさも良いです。

ラン花いろいろです。
細い花弁の紫花は当園の交配ではありませんが、バンダ×フウランの交配種です。
惜しむらくは香りがないのですが、さらにフウランと交配すれば香りが出てくるかも知れません。

ラン花のオードブルです。
写真を撮るためにばらばらにしてしまったので、水を入れた皿に盛ってみました。
明けましておめでとうございます。
今年は、東北大震災や福島原発災害に遭われた方々に、少しでも希望の陽がさす年になりますことを祈念いたします。
新年を迎えて家の周りにある植物たちを見てみました。
これらの植物のように、自然のままに気持ちゆったりと過ごしていきたいものです。

鉢植えのクリスマスローズに力強い花芽が伸びています。
これも花咲Jが交配したものですが、初花はどんな花が咲くやら・・楽しみです。

柿の木の株元に植えたクリスマスローズの方は、まだ小さな花芽です。
家の西側にあり、家の影と柿の葉で日光は遮られる場所ですが、大きな葉を付けています。
花は茶色系のイマイチかイマニくらいですが、咲くとかわいいです。
冬に咲く花として貴重な花です。

道端に生えたローズマリー
当宅西側の道路との境界線上に実生したものですが、横にあるコンクリート擁壁の上にはローズマリーが植えてあるため、こぼれ種から発芽したと思います。
コンクリートの隙間は数ミリしかないのにも関わらず、幹は直径2cm近くの太さで、冬に青い小花を咲かせてくれます。
花咲Jが車にひかれないよう、道路側へ伸びる枝はすべて切り取り、盆栽風に剪定しています。

ホームページにたびたび登場しているヘゴ着けランです。
右側のミニカトレアは10月24日に既に咲いていたものですが、もう50日間も咲き続けています。
干からびてドライフラワーになってしまったかと心配するときがあります。
ランは不定期に年2回咲くものがよくありますが、秋頃から寒い季節に向けて咲く花は同株でも花持ちがいいです。
バルブを増やして成長するタイプのランは、新バルブ毎に一つの花を付けます。
中には年中成長するものもありますが、冬を越して暖かくなるに従って成長したり、真夏の暑さで休眠して涼しくなって成長を始めたり、一つのバルブが出芽から成熟するまで1年間を要さないため、花を何回も楽しめます。
2012.1.10 冬の園芸作業いろいろ
冬は植物も休眠状態のものが多く、世間一般的にはあまり園芸作業も活動的ではありません。
施設園芸農家として再出発した花咲Jは、年中こなしきれない色んな作業に明け暮れています。
いよいよ皇帝ダリアも終演?の時を迎えました。
メキシコ原産の植物とあって、日本では寒さに耐えられないようです。
12月であっても霜に当たると即、葉が縮れて黒変してしまいます。
今冬は1月2日になるとほとんどすべての葉が縮れてしまいました。
2日の朝、コンクリート地面が少し濡れていたことから、夜中にみぞれでも降ったのかも知れません。

霜に当たったのか、葉が縮れてしまった皇帝ダリアです。
今日(8日)は1年間いろいろと楽しませてくれた皇帝ダリアを伐採します。

葉腋に伸びた新芽には大きく膨らんだつぼみも見えますが、新芽の葉も縮れてしまい、花が開くことは不可能です。
1年経たずして最大高さ3m以上にまで伸びた9本の幹を、地上約30cmで伐採しました。
幹は太いのですが、草本ゆえにのこぎりで簡単に切れます。
欲の深いじいさんは幹を節々で細かく切り、挿し木としました。
生命力の旺盛な皇帝ダリアは、寒中に挿し木して春にはもう新芽と根が出てきます。
挿し木は霜に当てないことと、凍らない温度が保てられればよいです。

前回記載の道端に生えたローズマリーですが、陽もうららかな本日(10日)花咲Jが美術的センスも剪定技術もないまま(本人は多少なりともあるように思っている。)散髪いたしました。
枝間が透いてさっぱりしたような感じです。

住宅西面の道路端という厳しい環境と危険のなか、今年も車に轢かれず、元気でいてもらいたいものです。

道端盆栽ローズマリーの花芽もだいぶ切り落としてしまいましたが、小さくて目立たないとは言え、青色の小花(長さ12mm)をたくさん咲かせます。
ローズマリーの枝先はハーブとして肉を焼く時の香味料などになります。
花は小さくとも、花の少ない冬に咲くのが取り柄です。
乾燥した土壌を好む常緑低木で、ハーブであるせいか病害虫もほとんど寄り付きません。
苗木を定植すると成長は旺盛で、樹形を保つには年2回くらいの剪定が必要になります。
その点、鉢植えは根の成長も制限されるせいか、それほどの剪定は必要になりません。
今まではさほど手入れしなかったのですが、道路端にあって通行人の人々にも見られるため、小奇麗にと一応剪定してみました。
水苔植えのランは正月から植え換え作業に入ります。
この時期の植え換えはちょっと早いのですが、量を多くこなすにはやむを得ません。
花咲Jはサラリーマン時代、あまりランに手をかけられず、植え換えもせずに水だけやっていたような状況だったので、鉢植えの蘭の根が縦横に絡み合い手がつけられない有様のものもあります。
植え込む時間と同じくらいに根をほぐす時間がかかります。
でも、この植え換えが園芸の一番の楽しみのような気もします。
2012.1.29 農繁期
当園、園芸楽の農家としての農繁期は正月から始まり、5月くらいまで植え換え作業などが続きます。
花咲Jはサラリーマン時代に満足な管理ができなかったため、温室内のすべての鉢を植え換えたいのですが・・。
特に水苔で植えてあるランは10年以上、植え換えていないものが多くあり、それらは本体が鉢を乗り越えて、中には二つ先の鉢まで行って生きているものもあります。
そうなると鉢内の水苔は黒い粉状になるために根は鉢内へ向かって伸びず、鉢上を縦横に伸び回り、植え換え時にそれをほぐすのは知恵の輪を解くように時間がかかります。
フウランのような単茎種はこのような状況でも何とか枯れずに生きていますが、バルブが増えて伸びていくものや地生蘭は枯れるものも多くなります。
さらに悪いことに、この時期はスキーシーズンと重なり、身体のあちこちに古傷のある花咲Jはそれでも老体の自覚が薄く、ふらりと日帰りスキーへ出かけてはふらふらになって帰ってきます。
園芸楽の農繁期はこういう状態で非常に忙しい有様です。
昨年の植え換えからヘゴ着けをこつこつと作っていますが、ヘゴ着けランのページにありますように、しっかり着生するまでにはやはり2年以上の栽培管理を要します。
作成したものを販売品コーナーへリストアップしたくてもできない状態で、ヘゴ着け以外の植え換えも遅れてしまうために焦りも感じている次第です。

再々登場のミニカトレアで3ヶ月も咲き続けています。
写真左側の1花は花弁に汚れが出てきました。
ミニカトレアでも小輪の花は特に長持ちします。
冬にかけて、温室ではなく寒い場所で咲いてくれると長い間、楽しませてくれます。
このヘゴ着けは家の敷地内にある小さなガラスフレームに入れてあり、加温はしません。
洋ランなども長年かけて徐々に低温に慣らすと、品種にもよりますが、結構、耐寒性が出てきます。
昔、無加温の車庫内で大輪のカトレアを何鉢か作っていた時に、一晩マイナス4〜5℃まで下がった日があり、1日ですべて枯れてしまいました。

秋から冬にかけて園芸店でパンジーなどとともに売られているアリッサムです。
花が小さくて、以前はあまり好きな花ではありませんでしたが、植えてみると1株で直径30cm以上に育ち、なかなか強い香りを出すため、最近は毎冬、鉢やプランターに植えています。
日当たりを好む草花で、5月まで楽しませてくれます。

1月8日に伐採した皇帝ダリアの挿し木の様子です。
長さ10cm程度に切断してあり、節(葉柄)から芽を出しますが、根はどこから出るのでしょう。
茎の切断面か、節部か、発根に成功したら確認してみます。

アリドオシの実です。
小さな木では実が付かず、付いてもまばらに付くことが多いです。
葉柄に鋭いとげがあり、時々ちくちくと刺されますが小さくて(写真は直径6mm)かわいい実です。

クンシランの実です。
草姿が大きいために実も大きくなります。
現在、実が色づき始めていますが、オモトなどに比較すると色・形が今一つの感じです。

この時期に咲くミニカトレアです。
鉢を持ち出したくても棚上で根が絡まりあい取り出せません。
切り花で出荷することもありますが、また写真を撮ってみました。
日本に自生するランの花は日本人の感性に合ってとても良いのですが、洋ランの華やかさも良いです。

ラン花いろいろです。
細い花弁の紫花は当園の交配ではありませんが、バンダ×フウランの交配種です。
惜しむらくは香りがないのですが、さらにフウランと交配すれば香りが出てくるかも知れません。

ラン花のオードブルです。
写真を撮るためにばらばらにしてしまったので、水を入れた皿に盛ってみました。
今日(8日)は1年間いろいろと楽しませてくれた皇帝ダリアを伐採します。
枝間が透いてさっぱりしたような感じです。
写真左側の1花は花弁に汚れが出てきました。
ミニカトレアでも小輪の花は特に長持ちします。
冬にかけて、温室ではなく寒い場所で咲いてくれると長い間、楽しませてくれます。
このヘゴ着けは家の敷地内にある小さなガラスフレームに入れてあり、加温はしません。
洋ランなども長年かけて徐々に低温に慣らすと、品種にもよりますが、結構、耐寒性が出てきます。
昔、無加温の車庫内で大輪のカトレアを何鉢か作っていた時に、一晩マイナス4〜5℃まで下がった日があり、1日ですべて枯れてしまいました。
花が小さくて、以前はあまり好きな花ではありませんでしたが、植えてみると1株で直径30cm以上に育ち、なかなか強い香りを出すため、最近は毎冬、鉢やプランターに植えています。
日当たりを好む草花で、5月まで楽しませてくれます。
長さ10cm程度に切断してあり、節(葉柄)から芽を出しますが、根はどこから出るのでしょう。
茎の切断面か、節部か、発根に成功したら確認してみます。
小さな木では実が付かず、付いてもまばらに付くことが多いです。
葉柄に鋭いとげがあり、時々ちくちくと刺されますが小さくて(写真は直径6mm)かわいい実です。
草姿が大きいために実も大きくなります。
現在、実が色づき始めていますが、オモトなどに比較すると色・形が今一つの感じです。
鉢を持ち出したくても棚上で根が絡まりあい取り出せません。
切り花で出荷することもありますが、また写真を撮ってみました。
日本に自生するランの花は日本人の感性に合ってとても良いのですが、洋ランの華やかさも良いです。
細い花弁の紫花は当園の交配ではありませんが、バンダ×フウランの交配種です。
惜しむらくは香りがないのですが、さらにフウランと交配すれば香りが出てくるかも知れません。
写真を撮るためにばらばらにしてしまったので、水を入れた皿に盛ってみました。