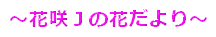
2月分

当園自家交配種(万里紅×赤花系セッコク)のセッコクが咲き出しました。
去年ヘゴ着けにしたものです。
普通のセッコクよりも開花時期が早いため、洋ラン系デンドロビウムの遺伝子が入っているような気がします。
・ 2013.2.22 春遠からじ
| 戻る | トップへ | 販売品コーナーへ | 購入のご案内へ | 送料のご案内へ | お問い合わせへ | レポートコーナーへ |
2013.2.22 春遠からじ
寒さにじっと耐えてきた植物も、次に来るであろう春に備えて力を全身に溜めているように見えます。
平均気温は1月10日前後を底にして毎日0.1℃程、日照時間もその前から少しずつ増えているのですが、それらを敏感に感じ取っているのかも知れません。
無加温の温室(温室とは言えませんが・・)でも寒風や霜から逃れられるために、この時期くらいから雑草の伸びが加速されます。
地面に置いた小さな鉢などは2〜3週間も経つと、草に覆われて日光を遮られてしまいます。
これから初夏くらいまで、度々の草取りが欠かせません。
そんな雑草に交じってシダ類もよく生えてきます。
雑草としてのシダが多いのですが、中には鉢植えにしていた園芸植物のシダ植物(ノキシノブ・マツバラン等)も胞子がこぼれて幼苗が地面や鉢の中のあちこちに生えてきます。
マツザカシダも温室内の地面に多数の幼苗が発生し、引き抜くと根が細かくて多いため多量の土ごと剥がれて困ります。
このシダは日本の山地里山にごく普通に見られるオオバノイノモトソウの斑入り変種のようですが、かなりの数のマツザカシダが全国各地で散見されるようです。
他の植物の斑入り変種は出現率が極めて低く、さらに斑入り種の実生は原種に戻る確率が高いのですが、マツザカシダの実生はほとんどが斑模様を遺伝するようです。
当園にあるマツザカシダの最初は、花咲Jが昔園芸店で1鉢購入したものですが、自然にできた胞子を温室中に飛散させて多数の実生(斑入り葉種)が毎年発生します。
ノキシノブ・マツバランの実生は地面には出ませんが、それと反対にマツザカシダは鉢内には出ず、地面に苗が出てきます。
実生後4〜5年経つと株の葉の直径が50〜60cmにも育ち、他の園芸植物を覆ってしまうので雑草として抜かざるを得ません。
ここ数年は大きくなってしまった株を抜くより、2〜3月に出てくる胞子葉をハサミで切って済ますこともあります。
せっかく生えたものを鉢上げしようと思って何回か鉢に移植したのですが、容易に鉢の中で根付いてくれません。
同じシダでもノキシノブ等は水切れで葉がチリチリになっても水を与えると復活してとても強いのですが、マツザカシダは一度の水切れで枯れ死することが多いです。
マツザカシダは葉の斑模様が美しく、夏の観葉植物として微風に揺れる涼しげな葉の鑑賞価値は高く、好ましい山草植物のひとつです。
今年はこの胞子を採集して鉢等に蒔いてみようと思います。
成功すれば鉢上げの問題が片付くという魂胆です。

温室横の狭い空地にある自家菜園に生えたスイセンが元気に花を咲かせました。
畑とは言え全く管理が行き届かず、秋にニンニクやワケギを植えたのですが、雑草の中に埋もれてどこに葉があるのかさえ分かりません。
このスイセンの半分くらいにでも育ってくれればありがたいのですが、放ったらかしでは無理な話です。

春の七草のホトケノザです。
この葉の形が仏様のお座りになる蓮座に似ていることからつけられた名前とのことです。
よく見ると、葉とともに花も何となく観音様に見えてしまいます。
そのようなありがたい名前や姿の植物なのに、温室の内外や畑に生え過ぎるのが困るところです。

今年は早く咲いたのか遅いのか、記録もなくて分かりませんが、温室脇の白梅が咲き出しました。
遠くで見るには桜にかないませんが、近くで見ると丸々とふくよかなつぼみやかすかな香りが春爛漫の先駆けとして十分な味わいを見せてくれます。

ウメに合わせてツバキも咲き出しましたが、時として強く吹く北風や寒波に遭うと花びらがすぐに傷んで茶色くなってしまいます。
つやのある葉と大きく派手な花も日本人が古来から見慣れているせいか、やはり日本的な植物という感じです。

上のツバキよりも2〜3週間早く咲き出しました。
こちらも北風と寒波にやられて無傷の花はほとんどありません。
木の北側に温室の外壁があり、西風、北風も防げる場所にあるのですが・・。

鉢植えの斑入りツバキは年中温室内にあるため花は無傷です。
一昨年に挿し木用として枝を切り取ったため、去年は花が咲かず、今年は1輪だけ花が咲きました。

玄関の外に置いた鉢植えのクリスマスローズです。
クリスマスローズの中でも地味な花色ですが、花が咲くと目につく場所に置きたくなります。

いつも出てくるミニカトレアです。
現在3花目(裏側)が開花しましたが、写真の1花は1月13日、隣の1花が2月9日に開きました。
この両日とも横に置いてある最高最低温度計がマイナス1℃を記録した日に開花しました。
葉や花の大きなカトレアは氷点下に耐えないと思いますが、ミニカトレアは年月をかけて乾燥気味に管理すると結構耐寒力がつくようです。

当園自家交配種のクリスマスローズ八重咲きの初花です。
開花後、日数が経ち、おしべはほとんど落ちてしまっています。
数年前から交配した種を蒔き始めて今年あたりから初花が咲き始めました。
花色や形を意図した交配ではないのですが、ダブルが咲いてくれました。

ヘゴ着けのフウラン交配種「藤娘」の花が咲き続けています。
1月に入ってから咲き出し、現在も3花茎が開花中ですが、つぼみも3花茎あります。
冬の開花はつぼみが開くまで長期間かかり、開いてからもドライフラワーになってしまったかと思うほど咲き続けます。

加温設備のない小温室(?)に置いてあるクンシランの花芽が伸びだしました。
小温室は遮光してありますが日当たりもよく、1日の気温変化は冬がマイナス1℃〜30℃と激しい場所になっています。
最高気温を下げたいのですが、換気扇の容量不足です。

実生約5年生の初花のつぼみです。
クンシランには黄花等もありますが、当園にあるのは普通の橙花です。
普通花でもよく見ると色の濃淡や抱え咲き、花弁の広狭等の花形の変化があります。

温室内の地面に生えている実生のマツザカシダです。
写真は胞子を付けない栄養葉です。
胞子を付ける胞子葉の後に出てくる葉で、葉幅が広く葉柄も短くて、形よく株元を飾ります。

マツザカシダの胞子葉です。
斑模様は栄養葉と同様ですが、葉幅が細く、葉柄が直立して50cm以上に伸び、葉裏の縁に沿って胞子を付けます。

株元で展開する栄養葉に比較して数段高く直立します。
この姿もいいのかも知れませんが、鉢植えにした場合ちょっとアンバランスです。
まだ寒さの厳しい2月ですが、植物も少しずつ変化を見せています。
寒さにじっと耐えてきた植物も、次に来るであろう春に備えて力を全身に溜めているように見えます。
平均気温は1月10日前後を底にして毎日0.1℃程、日照時間もその前から少しずつ増えているのですが、それらを敏感に感じ取っているのかも知れません。
無加温の温室(温室とは言えませんが・・)でも寒風や霜から逃れられるために、この時期くらいから雑草の伸びが加速されます。
地面に置いた小さな鉢などは2〜3週間も経つと、草に覆われて日光を遮られてしまいます。
これから初夏くらいまで、度々の草取りが欠かせません。
そんな雑草に交じってシダ類もよく生えてきます。
雑草としてのシダが多いのですが、中には鉢植えにしていた園芸植物のシダ植物(ノキシノブ・マツバラン等)も胞子がこぼれて幼苗が地面や鉢の中のあちこちに生えてきます。
マツザカシダも温室内の地面に多数の幼苗が発生し、引き抜くと根が細かくて多いため多量の土ごと剥がれて困ります。
このシダは日本の山地里山にごく普通に見られるオオバノイノモトソウの斑入り変種のようですが、かなりの数のマツザカシダが全国各地で散見されるようです。
他の植物の斑入り変種は出現率が極めて低く、さらに斑入り種の実生は原種に戻る確率が高いのですが、マツザカシダの実生はほとんどが斑模様を遺伝するようです。
当園にあるマツザカシダの最初は、花咲Jが昔園芸店で1鉢購入したものですが、自然にできた胞子を温室中に飛散させて多数の実生(斑入り葉種)が毎年発生します。
ノキシノブ・マツバランの実生は地面には出ませんが、それと反対にマツザカシダは鉢内には出ず、地面に苗が出てきます。
実生後4〜5年経つと株の葉の直径が50〜60cmにも育ち、他の園芸植物を覆ってしまうので雑草として抜かざるを得ません。
ここ数年は大きくなってしまった株を抜くより、2〜3月に出てくる胞子葉をハサミで切って済ますこともあります。
せっかく生えたものを鉢上げしようと思って何回か鉢に移植したのですが、容易に鉢の中で根付いてくれません。
同じシダでもノキシノブ等は水切れで葉がチリチリになっても水を与えると復活してとても強いのですが、マツザカシダは一度の水切れで枯れ死することが多いです。
マツザカシダは葉の斑模様が美しく、夏の観葉植物として微風に揺れる涼しげな葉の鑑賞価値は高く、好ましい山草植物のひとつです。
今年はこの胞子を採集して鉢等に蒔いてみようと思います。
成功すれば鉢上げの問題が片付くという魂胆です。

温室横の狭い空地にある自家菜園に生えたスイセンが元気に花を咲かせました。
畑とは言え全く管理が行き届かず、秋にニンニクやワケギを植えたのですが、雑草の中に埋もれてどこに葉があるのかさえ分かりません。
このスイセンの半分くらいにでも育ってくれればありがたいのですが、放ったらかしでは無理な話です。

春の七草のホトケノザです。
この葉の形が仏様のお座りになる蓮座に似ていることからつけられた名前とのことです。
よく見ると、葉とともに花も何となく観音様に見えてしまいます。
そのようなありがたい名前や姿の植物なのに、温室の内外や畑に生え過ぎるのが困るところです。

今年は早く咲いたのか遅いのか、記録もなくて分かりませんが、温室脇の白梅が咲き出しました。
遠くで見るには桜にかないませんが、近くで見ると丸々とふくよかなつぼみやかすかな香りが春爛漫の先駆けとして十分な味わいを見せてくれます。

ウメに合わせてツバキも咲き出しましたが、時として強く吹く北風や寒波に遭うと花びらがすぐに傷んで茶色くなってしまいます。
つやのある葉と大きく派手な花も日本人が古来から見慣れているせいか、やはり日本的な植物という感じです。

上のツバキよりも2〜3週間早く咲き出しました。
こちらも北風と寒波にやられて無傷の花はほとんどありません。
木の北側に温室の外壁があり、西風、北風も防げる場所にあるのですが・・。

鉢植えの斑入りツバキは年中温室内にあるため花は無傷です。
一昨年に挿し木用として枝を切り取ったため、去年は花が咲かず、今年は1輪だけ花が咲きました。

玄関の外に置いた鉢植えのクリスマスローズです。
クリスマスローズの中でも地味な花色ですが、花が咲くと目につく場所に置きたくなります。

いつも出てくるミニカトレアです。
現在3花目(裏側)が開花しましたが、写真の1花は1月13日、隣の1花が2月9日に開きました。
この両日とも横に置いてある最高最低温度計がマイナス1℃を記録した日に開花しました。
葉や花の大きなカトレアは氷点下に耐えないと思いますが、ミニカトレアは年月をかけて乾燥気味に管理すると結構耐寒力がつくようです。

当園自家交配種のクリスマスローズ八重咲きの初花です。
開花後、日数が経ち、おしべはほとんど落ちてしまっています。
数年前から交配した種を蒔き始めて今年あたりから初花が咲き始めました。
花色や形を意図した交配ではないのですが、ダブルが咲いてくれました。

ヘゴ着けのフウラン交配種「藤娘」の花が咲き続けています。
1月に入ってから咲き出し、現在も3花茎が開花中ですが、つぼみも3花茎あります。
冬の開花はつぼみが開くまで長期間かかり、開いてからもドライフラワーになってしまったかと思うほど咲き続けます。

加温設備のない小温室(?)に置いてあるクンシランの花芽が伸びだしました。
小温室は遮光してありますが日当たりもよく、1日の気温変化は冬がマイナス1℃〜30℃と激しい場所になっています。
最高気温を下げたいのですが、換気扇の容量不足です。

実生約5年生の初花のつぼみです。
クンシランには黄花等もありますが、当園にあるのは普通の橙花です。
普通花でもよく見ると色の濃淡や抱え咲き、花弁の広狭等の花形の変化があります。

温室内の地面に生えている実生のマツザカシダです。
写真は胞子を付けない栄養葉です。
胞子を付ける胞子葉の後に出てくる葉で、葉幅が広く葉柄も短くて、形よく株元を飾ります。

マツザカシダの胞子葉です。
斑模様は栄養葉と同様ですが、葉幅が細く、葉柄が直立して50cm以上に伸び、葉裏の縁に沿って胞子を付けます。
