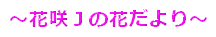
2013年5月分

バンダ×富貴蘭に当園にて風蘭を戻し交配した品種です。
風蘭より少し大型の葉と花で、きれいな花色とかすかな芳香があるため気に入っているのですが、なぜか数株しかありません。
昔のことで定かではありませんが、フラスコ内にカビが繁殖してほとんど残らなかったのかも知れません。
・ 2013.5.20 女性樹木医
| 戻る | トップへ | 販売品コーナーへ | 購入のご案内へ | 送料のご案内へ | お問い合わせへ | レポートコーナーへ |
2013.5.20 女性樹木医
静岡県浜松市には日本の女性樹木医第1号となった塚本こなみ氏がいます。
氏は市内の造園家に嫁ぎ、21年前に樹木医の資格を取られてからは、巨樹古木の診断治療、移植や造園、設計施工等を行い、植物園入場者数日本一と言われる「あしかがフラワーパーク」に巨大藤を移植後、同パークの園長を務め、テレビ等にも多数出演されています。
* 参考(あしかがフラワーパーク・藤の開花時期の入場者1日7万人・1996年移植時の藤は幹周3m65cm、250畳の大きさのものを20km移動、2008年では幹周4m15cm、棚の広さ600畳とのことです。)
氏と同年代で同じ地域に住み、植物に対して興味心が強く、植物に関わる仕事をしている点でも共通点のある花咲Jとは、残念ながらレベルが遠くかけ離れ全くの面識もありません。
しかし、そういう方が今年から集客数の減少に悩む浜松市フラワーパークに民間人として初めての公社理事長に就任したことは朗報です。
氏は足利市と浜松市を掛け持ちで運営されているようです。
今年から浜松市フラワーパークは花等の観賞季節に合わせて変動する入園料とするそうです。
簡単に動かせない樹木も多いことから、行ってはみたがあいにく花等の少ない時季に入園料が安いなら納得もできるでしょう。
広い園内(30万㎡)には多種(3,000種)の花や草木があり、植物園としても通年楽しめる施設です。
公に認められた樹木医でなくても、長年ランを育ててきた花咲Jとしては、せめて蘭医でありたいと願っているのですが、このところランの臨終をみとるホスピス医の状況が多いのはどうしたことでしょう。
* 参考(浜松市フラワーパーク入園料は6月20日ごろまで大人700円となっており、この時季の見どころを市の各戸配布広報誌から転載しました。)

用紙が薄いために裏が透けて見えてしまいました。

川堤の土手下の草を刈った5月2日には、高さ10cmもないような大きさだった皇帝ダリアですが、19日には30cm以上に伸びました。
宿根草ですが昨冬は寒さが厳しかったせいか、9本のうち3本は枯れてしまったようです。

温室のある敷地内の一角に自然に生えたモッコクです。
高さは約2mくらいで、若木のせいか極端に切りつめても切りつめても成長力旺盛で、今年も花を咲かせました。
梅干し弁当のように中心に紅をさし、鼻を近づけると良い匂いがします。

花だより4月分でご紹介しましたスノーダンサーの花です。
今まであまりよく観察していなかったのですが、距を上へ跳ね上げる特徴があると分かりました。

一昨年、鉢植えから地植えにしたボタンの根元から台木のものと思われるひこ生えが出てきました。

ひこ生えを切り取ったところです。
ボタンの台木にはシャクヤクを使うと聞いています。
もしこれを植えて根付いたら、園芸品種のような花は咲かないとしてもシャクヤクの花が見られるかもしれないと思い、再度植えることにしました。

植えてはみましたが、途中で切れて棒のような根があるだけでは、根付くのは無理かも知れません。

今年も元気なローズマリーの道端盆栽です。
花咲Jの頭髪は勢いがなくなるばかりなのに、コンクリートのわずかな隙間に生えたローズマリーは去年も散髪したのに、厳しい環境でもなぜこんなにフサフサになるのでしょう。

成長が良すぎて太り過ぎるとかえって心配もあるので、また思い切りバッサリと散髪してしまいました。

そのすぐ横に自然実生のローズマリーが1本芽生えてきました。(写真手前)
乾燥する環境を好むと言われていますので、たしかにその条件には合っていると思うのですが・・・。

ヘゴ着け2年後のフウランです。
フウランの生長はとてもゆっくりで、葉はいつ見ても変化を感じられないのですが、花と根の活動時は日々生長の様子が見られます。
特に根の活動初期は、ランの生命力を感じさせてくれます。

根先がほんの狭い空間にも潜り込んでいく様子を見ていると、その柔軟性や強い接着力とともに、どんな暴風にも豪雨にも落ちずにしがみつく能力に感心させられます。
夏場に若干のエサやりのみで雇っているビニールハウスの用心棒ガンマー之助の近況です。
去年秋以降、ガンマー之助は半年以上も姿を見ていないのですが、4月12日の水やり時に初鳴き声を聞いてから、5~6日毎の水やりの都度、雨が降ってきたと喜んでいるのか鳴き声であいさつしてくれます。
鳴き声だけですが、このハウス内ではガンマー之助のほかにカエルは見たことがないからガンマー之助に間違いないと思います。
5月2日の水やり時には鳴き声がなかったので気になりましたが、その後はまたあいさつしてくれて、特に5月19日はとりわけ甲高い近所迷惑になろうかという声で2度に渡って長く鳴きました。
毎回、鳴き声がするあたりを探してみるのですが、姿は見えず土の中で鳴いているのかも知れません。
もっとも、今出会ってもエサとなるバッタ類はいなくて、おやつとして与えられないから困るのですが・・・。
ガンマー之助が今年も生きていることを確認できて安心しています。
静岡県浜松市には日本の女性樹木医第1号となった塚本こなみ氏がいます。
氏は市内の造園家に嫁ぎ、21年前に樹木医の資格を取られてからは、巨樹古木の診断治療、移植や造園、設計施工等を行い、植物園入場者数日本一と言われる「あしかがフラワーパーク」に巨大藤を移植後、同パークの園長を務め、テレビ等にも多数出演されています。
* 参考(あしかがフラワーパーク・藤の開花時期の入場者1日7万人・1996年移植時の藤は幹周3m65cm、250畳の大きさのものを20km移動、2008年では幹周4m15cm、棚の広さ600畳とのことです。)
氏と同年代で同じ地域に住み、植物に対して興味心が強く、植物に関わる仕事をしている点でも共通点のある花咲Jとは、残念ながらレベルが遠くかけ離れ全くの面識もありません。
しかし、そういう方が今年から集客数の減少に悩む浜松市フラワーパークに民間人として初めての公社理事長に就任したことは朗報です。
氏は足利市と浜松市を掛け持ちで運営されているようです。
今年から浜松市フラワーパークは花等の観賞季節に合わせて変動する入園料とするそうです。
簡単に動かせない樹木も多いことから、行ってはみたがあいにく花等の少ない時季に入園料が安いなら納得もできるでしょう。
広い園内(30万㎡)には多種(3,000種)の花や草木があり、植物園としても通年楽しめる施設です。
公に認められた樹木医でなくても、長年ランを育ててきた花咲Jとしては、せめて蘭医でありたいと願っているのですが、このところランの臨終をみとるホスピス医の状況が多いのはどうしたことでしょう。
* 参考(浜松市フラワーパーク入園料は6月20日ごろまで大人700円となっており、この時季の見どころを市の各戸配布広報誌から転載しました。)


川堤の土手下の草を刈った5月2日には、高さ10cmもないような大きさだった皇帝ダリアですが、19日には30cm以上に伸びました。
宿根草ですが昨冬は寒さが厳しかったせいか、9本のうち3本は枯れてしまったようです。

温室のある敷地内の一角に自然に生えたモッコクです。
高さは約2mくらいで、若木のせいか極端に切りつめても切りつめても成長力旺盛で、今年も花を咲かせました。
梅干し弁当のように中心に紅をさし、鼻を近づけると良い匂いがします。

花だより4月分でご紹介しましたスノーダンサーの花です。
今まであまりよく観察していなかったのですが、距を上へ跳ね上げる特徴があると分かりました。

一昨年、鉢植えから地植えにしたボタンの根元から台木のものと思われるひこ生えが出てきました。

ひこ生えを切り取ったところです。
ボタンの台木にはシャクヤクを使うと聞いています。
もしこれを植えて根付いたら、園芸品種のような花は咲かないとしてもシャクヤクの花が見られるかもしれないと思い、再度植えることにしました。

植えてはみましたが、途中で切れて棒のような根があるだけでは、根付くのは無理かも知れません。

今年も元気なローズマリーの道端盆栽です。
花咲Jの頭髪は勢いがなくなるばかりなのに、コンクリートのわずかな隙間に生えたローズマリーは去年も散髪したのに、厳しい環境でもなぜこんなにフサフサになるのでしょう。

成長が良すぎて太り過ぎるとかえって心配もあるので、また思い切りバッサリと散髪してしまいました。

そのすぐ横に自然実生のローズマリーが1本芽生えてきました。(写真手前)
乾燥する環境を好むと言われていますので、たしかにその条件には合っていると思うのですが・・・。

ヘゴ着け2年後のフウランです。
フウランの生長はとてもゆっくりで、葉はいつ見ても変化を感じられないのですが、花と根の活動時は日々生長の様子が見られます。
特に根の活動初期は、ランの生命力を感じさせてくれます。

根先がほんの狭い空間にも潜り込んでいく様子を見ていると、その柔軟性や強い接着力とともに、どんな暴風にも豪雨にも落ちずにしがみつく能力に感心させられます。
夏場に若干のエサやりのみで雇っているビニールハウスの用心棒ガンマー之助の近況です。
去年秋以降、ガンマー之助は半年以上も姿を見ていないのですが、4月12日の水やり時に初鳴き声を聞いてから、5~6日毎の水やりの都度、雨が降ってきたと喜んでいるのか鳴き声であいさつしてくれます。
鳴き声だけですが、このハウス内ではガンマー之助のほかにカエルは見たことがないからガンマー之助に間違いないと思います。
5月2日の水やり時には鳴き声がなかったので気になりましたが、その後はまたあいさつしてくれて、特に5月19日はとりわけ甲高い近所迷惑になろうかという声で2度に渡って長く鳴きました。
毎回、鳴き声がするあたりを探してみるのですが、姿は見えず土の中で鳴いているのかも知れません。
もっとも、今出会ってもエサとなるバッタ類はいなくて、おやつとして与えられないから困るのですが・・・。
ガンマー之助が今年も生きていることを確認できて安心しています。