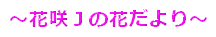
2017年1月分


左はミディカトレアのヘゴ着けです。
約5年前にヘゴに着けたもので、草体の割に大輪の花を咲かせます。
(年末にお客様にご購入いただいたものです。)
右は鮮やかな黄色一色のカトレアで、バルブ長約30cmのためミディとも言える品種です。
約5年前にヘゴに着けたものです。
少々背は伸びますが、強健な品種で花付き花持ちの良いタイプです。
(こちらも年末にお客様にご購入いただいたものです。)
・ 2017.1.1 冬に耐え
| 戻る | トップへ | 販売品コーナーへ | 購入のご案内へ | 送料のご案内へ | お問い合わせへ | レポートコーナーへ |
2017.1.1 冬に耐え
2017年の新年を迎えました。
年々暖冬化が進んでいるように感じますが、それでも時に厳しい寒さに震えあがることがあります。
厳しい寒さにさらされている野山を歩けば、わずかな陽の差す林床で、落ち葉にうずくまって赤い実を付けたヤブコウジを見かけます。
這うように伸びた茎を5〜10cmほど立ち上げ、4,5枚の葉に1個か2個付けた赤い実は、薄暗い林の中で鮮やかな彩りを添えています。
その横を歩いても気を付けていなければ、たいていは気付かずに通り過ぎるでしょう。
こんな小草も先人はよく観察して歌に詠み、園芸品種を選別し、正月にはめでたい飾りつけに添え草として使ってきました。
ヤブコウジの姿は小さいながら、常緑の小低木に分類されます。
江戸時代の園芸隆盛期には、その別名を「十両」と呼び、万両・千両・百両(カラタチバナの別名)・一両(アリドオシの別名)と実のなる小低木を愛玩したということです。
その中で千両だけは強健な性質のためか、変わりものを珍重する先人の時代から今に至るまで、黄色実があるのみで他に変化した園芸品種は見つからないようです。
植物の突然変異は滅多に起きることではないと思いますが、なぜ十両・百両・万両、また春蘭・寒蘭・風蘭・おもと等々、特定の種類に斑などの変わりものが存在するのか不思議です。
それらの変わりものは独特の味わいを見せ、古くから多くの人を魅了してきました。
こうした変化はその植物にとって偶然の産物と思うのですが、幾万の中からそれを見つけて価値を認めた先人にも感心します。
日本人はなぜそういうものを珍重する人が多いのか考えてしまいます。
まず始めに斑入り植物が自然の中に存在するからということは言えますが、日本は火山列島に付随する地震や台風等の自然災害が他の国より多いと言えます。
木造家屋に住み、昔から大火になることも多く、燃えてしまえば家も失うことになります。
そういうお国柄から自然災害被害へのあきらめ、耐えてしのぐなどという姿から、わびさびの心と通じて多くの日本人の性格に備わったのかも知れません。
自然災害が多くても、野山は豊富な自然にあふれ、日本人はそれらをよく観察し、余すところなく生活・文化に利用してきたと言えます。
細やかな観察眼は野にある草1本にも注がれて、自然の脅威に耐えて乗り越える姿に共感したのでしょうか。
百年余も前であれば現在の都会地でも、ごく近い所に雑木林等があったと思います。
野山で偶然に見つけることができた斑入り植物等は、日本人の好奇心を呼び起こすきっかけだったのでしょう。
万両・百両・十両と呼ばれた斑入り植物は、自然の気まぐれによる恵みとしか言えませんが、かなりの数の園芸品種が多くの日本人を魅了してきました。
原種はその原点であり、野山に自然実生した姿は日本の原風景といえるものでしょう。
そんな風景を探す野山歩きもよいものです。

風蘭×バンダの交配種のヘゴ着けで、ヘゴに着けて5年以上経過したものです。
株は少々大型となり、茎がヘゴを1周巻いていますが、その状態で最大全幅約31cm、上下59cmあります。
(こちらも年末にお客様にご購入いただいたものです。)

花は無香で淡い青紫色地に弁先と舌弁がやや濃色となります。
花の大きさは幅約6.5cm、上下約9cmあります。
春に咲いて、12月に2度目の開花です。

アリドウシ(一両)の斑入り品種です。
こちらも園芸品種はあまりないようですが、本品は約25年前に当市の園芸商人から購入したものです。
実生をすると、親と同様の斑入りが時々出ます。
また、本品は丸葉ですが、斑のない実生苗の葉は先の尖った卵円形・長楕円形等、いろいろに変化したものも出ます。
冬に熟す実は艶のある鮮紅色で直径は5〜7mmです。
実は、実の枝柄がごく短く、葉元に1〜3個を実らせます。
名前の由来として、アリをも刺すと言われるトゲは細く鋭く、その名前から千両万両有り通しと縁起を担いだようです。
関東以西の山地樹林下に自生するとなっていますが、当地方で見かけたことはまだありません。

カラタチバナ(百両)の爪覆輪で葉縁を多少下方へ下げる品種です。
原種に近い品種ですが、原種は平らな葉です。
冬に熟す実は艶のある鮮紅色で直径は8〜9mmです。
カラタチバナの実は持ちがよく、初夏に花が咲き実を結びますが、その後、秋まで1年以上の間、特に変化もなく付いています。

カラタチバナの赤木で白実の品種です。
葉は平葉の萌黄色で爪覆輪が入り、赤木のため幹はピンク色です。
赤木の芽出しは、葉・幹ともにピンク色で出て美しいです。
当園の実生から出た変異品ですが、他にもありそうな芸です。

昨年4月、自宅のモミジに着けたフウランの桃姫実生です。
写真は12月2日撮影ですが、モミジの葉はうどんこ病が発生して無残に枯れ落ちる寸前です。
葉が茂っている間は丁度良い日陰だったのが、直射日光が当たり始めました。
本種の葉は肉厚で斑もないため、冬の日光程度は問題ないと思われます。

大丈夫そうではありますが、着けて1年未満であることと寒冷紗が余っていたために、上部の枝から枝を利用して遮光をしてやりました。

シデコブシに着けた富貴蘭「御城覆輪」です。
こちらも葉が茂っている間は絶好の良い日陰だったのが、落葉とともに直射日光が当たり始めました。
富貴蘭の中では強い採光に向いている品種ですが、陽が当たり始めるようになって緑色部分が若干、色薄くなってきました。
4月に着けるまではフレーム内の遮光下にあり、強光線に慣れていないことも原因と思われます。

桃姫同様に今回は頭上に遮光ネットを掛けました。
次の冬には完全に活着し、遮光の必要はないと思います。
既に数本の根が幹に張り付いているため、ほぼ活着という状態です。
秋以降、庭木の水やりもたまにやる程度となり、庭木着け富貴蘭も晴天が続いた4,5日後に全体を濡らしてやる程度です。
ただし、常緑樹等の葉がある状態では、小雨が降ってもランが濡れない場合も度々あるので、活着までは配慮が必要です。
2017年の新年を迎えました。
年々暖冬化が進んでいるように感じますが、それでも時に厳しい寒さに震えあがることがあります。
厳しい寒さにさらされている野山を歩けば、わずかな陽の差す林床で、落ち葉にうずくまって赤い実を付けたヤブコウジを見かけます。
這うように伸びた茎を5〜10cmほど立ち上げ、4,5枚の葉に1個か2個付けた赤い実は、薄暗い林の中で鮮やかな彩りを添えています。
その横を歩いても気を付けていなければ、たいていは気付かずに通り過ぎるでしょう。
こんな小草も先人はよく観察して歌に詠み、園芸品種を選別し、正月にはめでたい飾りつけに添え草として使ってきました。
ヤブコウジの姿は小さいながら、常緑の小低木に分類されます。
江戸時代の園芸隆盛期には、その別名を「十両」と呼び、万両・千両・百両(カラタチバナの別名)・一両(アリドオシの別名)と実のなる小低木を愛玩したということです。
その中で千両だけは強健な性質のためか、変わりものを珍重する先人の時代から今に至るまで、黄色実があるのみで他に変化した園芸品種は見つからないようです。
植物の突然変異は滅多に起きることではないと思いますが、なぜ十両・百両・万両、また春蘭・寒蘭・風蘭・おもと等々、特定の種類に斑などの変わりものが存在するのか不思議です。
それらの変わりものは独特の味わいを見せ、古くから多くの人を魅了してきました。
こうした変化はその植物にとって偶然の産物と思うのですが、幾万の中からそれを見つけて価値を認めた先人にも感心します。
日本人はなぜそういうものを珍重する人が多いのか考えてしまいます。
まず始めに斑入り植物が自然の中に存在するからということは言えますが、日本は火山列島に付随する地震や台風等の自然災害が他の国より多いと言えます。
木造家屋に住み、昔から大火になることも多く、燃えてしまえば家も失うことになります。
そういうお国柄から自然災害被害へのあきらめ、耐えてしのぐなどという姿から、わびさびの心と通じて多くの日本人の性格に備わったのかも知れません。
自然災害が多くても、野山は豊富な自然にあふれ、日本人はそれらをよく観察し、余すところなく生活・文化に利用してきたと言えます。
細やかな観察眼は野にある草1本にも注がれて、自然の脅威に耐えて乗り越える姿に共感したのでしょうか。
百年余も前であれば現在の都会地でも、ごく近い所に雑木林等があったと思います。
野山で偶然に見つけることができた斑入り植物等は、日本人の好奇心を呼び起こすきっかけだったのでしょう。
万両・百両・十両と呼ばれた斑入り植物は、自然の気まぐれによる恵みとしか言えませんが、かなりの数の園芸品種が多くの日本人を魅了してきました。
原種はその原点であり、野山に自然実生した姿は日本の原風景といえるものでしょう。
そんな風景を探す野山歩きもよいものです。
